1章:カスハラとは?現場での実態と影響
カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客や取引先などの立場を利用して、従業員に対して理不尽な要求・暴言・威圧行為を繰り返すハラスメント行為のことを指します。
なぜ問題なのか?
- スタッフのメンタル不調や離職の要因になる
- 他の顧客へのサービス低下につながる
- 店舗のブランドイメージが悪化する
よくあるカスハラの具体例
- 大声で怒鳴る、物を叩く
- 個人攻撃(「名前を言え」「訴える」など)
- 無理な返品要求、土下座の強要
- 差別的発言や人格否定
- クレームを盾にした金品要求
店舗への影響
- 従業員の士気低下、離職率の上昇
- 店舗運営の混乱、他の顧客離れ
- 対応コスト・リスクの増大
カスハラは個人の問題ではなく「店舗全体の課題」。まずは共通認識を持つことが第一歩です。
第2章:法的観点と企業の対応方針の基礎知識
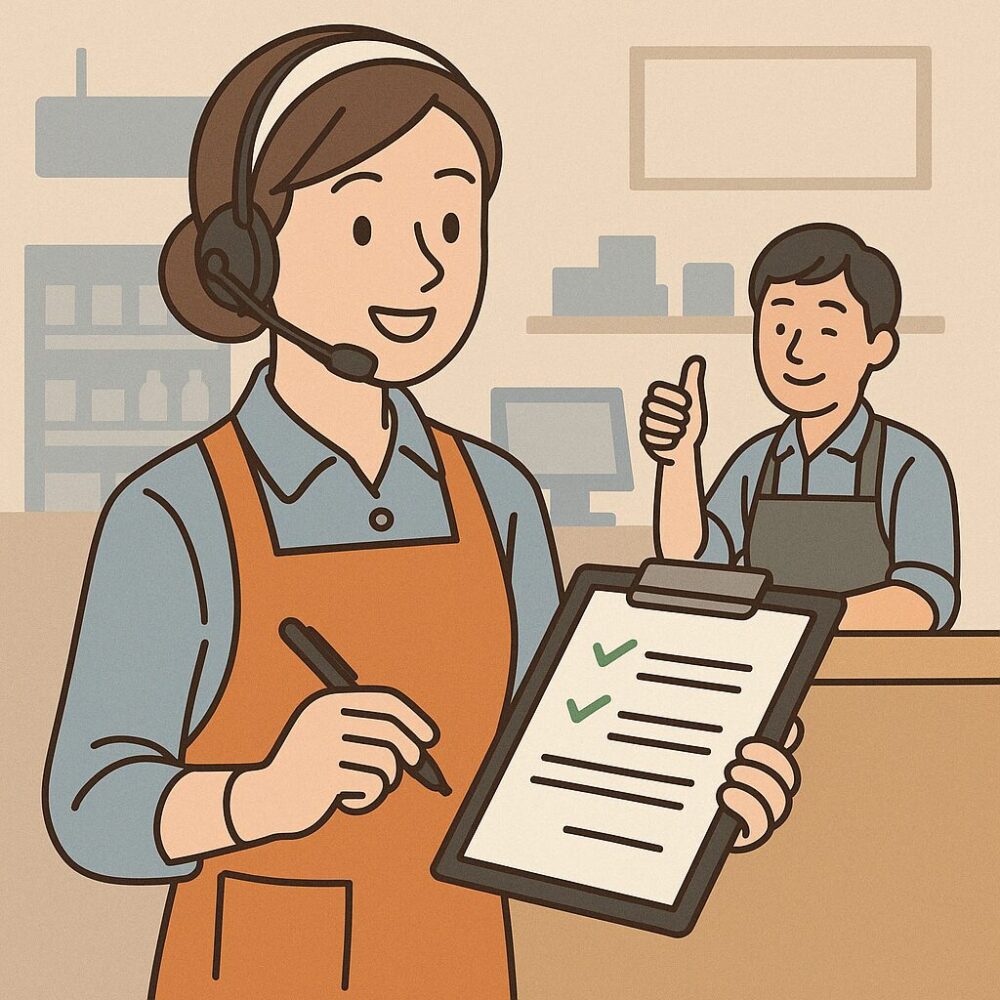
労働安全衛生法との関係
厚生労働省は2020年に「職場におけるパワーハラスメント防止措置」を義務化し、カスハラもパワハラの一種として扱われる場合があります。
企業に求められる対応
- ハラスメント方針の策定と周知
- 通報窓口・対応体制の整備
- 教育研修の実施
- 被害者への配慮措置
民事・刑事上の責任
悪質なケースでは、名誉毀損・業務妨害・脅迫・強要罪などに該当し、警察対応・告訴の対象となります。
ポイント
「泣き寝入り」が通用しない時代。現場スタッフだけに背負わせず、企業・管理者が仕組みとして守る必要があります。
第3章:スタッフ対応で信頼を勝ち取る!現場が実践できるカスハラ初期対応術

ステップ1:まずは落ち着く・感情的に反応しない
- NG対応:感情的に反論
- OK対応:「申し訳ございません。詳しくお伺いします」
感情に巻き込まれず、冷静なトーンで対応することが大前提。
ステップ2:事実確認を優先し、勝手に謝らない
- NG対応:「すみません」と即謝罪
- OK対応:「状況を確認させてください」
事実確認がスタッフを守る盾となる。
ステップ3:必要ならすぐ上司に引き継ぐ
- NG対応:1人で対応を続ける
- OK対応:「責任者をお呼びします」
判断を迷ったら即引き継ぎが鉄則。
ステップ4:周囲のお客様への配慮も忘れずに
- NG対応:放置する
- OK対応:「ご不快な思いをさせて申し訳ありません」
周囲の空気も“店舗評価”の対象。
ステップ5:対応後は必ず報告・共有する
- NG対応:何も報告せず終了
- OK対応:店長やチームに共有
報告文化がある職場はスタッフが孤立しない。
第4章:よくあるカスハラ事例【6〜10】と模範対応

事例6:大声での威嚇や叩き行動
- NG対応:「静かにしてください!」→ 火に油を注ぐ
- OK対応:「ご不便をおかけし申し訳ありません。すぐに対応します」
威圧行動には距離感と冷静さを持って。
事例7:「お前の名前は?訴えてやるからな」と個人攻撃
- NG対応:「私が悪いということですか?」と感情的に返す
- OK対応:「責任者よりご説明いたします」
組織対応を前面に出す。
事例8:同じ内容で何度も怒鳴り込み
- NG対応:「前にもご説明しましたが…」
- OK対応:「改めて確認の上、対応いたします」
「前にも」より「再確認」が鎮静化を導く。
事例9:「お前なんかクビにしてやる!」と脅す
- NG対応:「脅さないでください」
- OK対応:「責任者に共有いたします」
「自分1人で抱えていない」ことを示す。
事例10:退店後の電話やメールによる二次被害
- NG対応:「現場では問題なかったと思いますが」
- OK対応:「ご連絡ありがとうございます。内容を確認の上対応いたします」
“否定”より“受け止め”が大切。
第5章:よくあるカスハラ事例【16〜20】と模範対応
事例16:SNSでの晒し投稿をちらつかせて脅す
状況:「これ晒したらバズるよな?」「X(旧Twitter)に書いたら終わりだぞ」などと投稿を盾に無理な要求をする。
- NG対応:
「それは困ります!」と焦って過剰対応 - OK対応:
「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。ご要望を確認の上、責任者よりご対応させていただきます」
「SNSに書かれる恐怖」で萎縮しすぎないこと。冷静に組織対応を取ることが重要。
事例17:個室や裏へ呼び出そうとする行為
状況:「裏でちゃんと話そうか」「こっちに来い」と密室に誘導しようとする。
- NG対応:
「はい、わかりました」と従ってしまう - OK対応:
「そのような対応はいたしかねますので、こちらでお話を伺います」
スタッフの安全が最優先。「人目のある場所から動かない」判断が鉄則。
事例18:土下座など身体的屈辱を強要する
状況:「土下座しろ」「膝をついて謝れ」といった非人道的な要求をする。
- NG対応:
恐怖で黙ってしまう、あるいは形だけでも応じてしまう - OK対応:
「そのようなご要望にはお応えできません。責任者をお呼びいたします」
「人権侵害」は即時エスカレーション。毅然と拒否し、記録・証言を確保する。
事例19:頻繁に来店し、特定スタッフへのつきまとい
状況:毎日のように来店し、特定のスタッフを探して執拗に話しかける、監視するような行動を取る。
- NG対応:
「いつもありがとうございます…」と曖昧な態度 - OK対応:
「担当者は本日対応できかねます。必要であれば責任者が対応いたします」
ストーカー的な要素を感じたら即記録+本部連携。対応は必ず“組織の窓口”で行う。
事例20:防犯カメラ映像の開示を一方的に要求
状況:「カメラに映ってるはずだ。今すぐ見せろ」と店側の管理範囲を越えた要求をする。
- NG対応:
「映像はありますが…」と口を滑らせる - OK対応:
「防犯映像の開示は規定によりお受けしておりません。必要であれば所定の手続きをご案内いたします」
防犯映像は法律上、勝手に開示できない。方針を一貫して丁寧に説明する。
第6章:よくあるカスハラ事例【21〜25】と模範対応
事例21:商品に関係ない私的なことで怒鳴る
状況:「前に来たときの対応が悪かった!」「あの女がムカつく!」など、買い物と関係ない怒りをぶつける。
- NG対応:
「それは当店では対応できません」→ 事務的で冷たく感じられる - OK対応:
「ご不快な思いをされたとのこと、申し訳ございません。詳細を伺い、責任者より対応いたします」
私情の怒りにも“まず共感”→“責任者対応”が基本。話を否定せず、冷静に受け止める。
事例22:待ち時間に怒ってカートを投げる・棚を叩く
状況:混雑による待ち時間にイライラし、備品や什器を乱暴に扱う。
- NG対応:
「やめてください!」→ 威圧行動がエスカレートする危険あり - OK対応:
「申し訳ございません、お怪我のないようにお願いいたします。すぐにご案内いたします」
安全第一。スタッフは距離を保ち、暴力的行為の記録と上司への即時連絡が必要。
事例23:店外で待ち伏せや無断撮影をされる
状況:勤務後に駐車場などで待ち伏せされたり、スマホで無断撮影される。
- NG対応:
無視してしまい、報告も怠る - OK対応:
「安全確保のため、すぐ責任者にご報告いたします」とその場を離れる。後日詳細を共有。
プライベート侵害は“迷惑行為”の域を超える。被害感覚を正しく持ち、記録・共有が大切。
事例24:謝罪後もネチネチと繰り返し嫌味を言い続ける
状況:「さっき謝ったけど本当にわかってる?」「ああ、また同じミスするんだろ」など粘着型の言動。
- NG対応:
「何度も謝ってますけど…」→ 再燃させる火種に - OK対応:
「ご指摘を重く受け止めております。再発防止に努めます」
相手の“優位ポジション”への欲求を刺激しない対応が重要。低姿勢で終結を目指す。
事例25:「クビにさせた客が過去にいる」と脅す
状況:「前に1人クビにさせたんだよ」「本部に言えばお前も終わりだ」と過去の実績をちらつかせる。
- NG対応:
「そんなこと言われても…」と不安げな態度を見せる - OK対応:
「ご指摘について責任者に報告させていただきます」
「威嚇」は自信の揺らぎを狙っている。堂々と責任者対応へつなぐことでスタッフを守る。
第7章:よくあるカスハラ事例【26〜30】と模範対応
事例26:スタッフの私語や態度に過剰反応
状況:「ふざけてるのか?笑ってただろ」「接客中に私語とは何様だ」など、監視的に指摘される。
- NG対応:
「そんなつもりじゃありません!」と反論 - OK対応:
「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。以後、より丁寧に対応させていただきます」
ポイント:「否定」より「受け止め」の姿勢を。事実と異なっても感情を先に受け止める対応を。
「否定」より「受け止め」の姿勢を。事実と異なっても感情を先に受け止める対応を。
事例27:防犯タグ・万引き対策に逆ギレ
状況:タグの確認やブザーの誤作動などで「万引き扱いする気か!」と激高される。
- NG対応:
「疑ってるわけではありません」→ 逆に疑っている印象を与える - OK対応:
「安全管理上の確認でございます。ご協力ありがとうございます」
「システム上の確認」であると伝える。個人攻撃ではないことを丁寧に説明。
事例28:トラブルを他の客の前で故意に拡散
状況:「この店ひどいですよ!皆さん聞いて!」と大声で他の来店客に話しかけ始める。
- NG対応:
「静かにしてください!」→ 対立構造を助長 - OK対応:
「恐れ入りますが、こちらでお伺いしますので、ご移動をお願いできますか」
「状況の切り離し」が重要。周囲と分離し、冷静な対応空間をつくる。
ポイント:「状況の切り離し」が重要。周囲と分離し、冷静な対応空間をつくる。
事例29:レビューサイトや評価を盾に脅す
状況:「★1にしてやるぞ」「Googleマップに悪評書くぞ」とレビューを武器に不当要求。
- NG対応:
「やめてください!」と防御反応する - OK対応:
「ご意見は真摯に受け止め、今後の参考とさせていただきます」
ポイント:「書く自由」を否定せず、“受け止める姿勢”で軟着陸を図る。
「書く自由」を否定せず、“受け止める姿勢”で軟着陸を図る。
事例30:過去の不満を積み上げて爆発する
状況:普段は静かだったのに「前から思ってたけどさ…」と蓄積した怒りをまとめてぶつけてくる。
- NG対応:
「いまの件だけでご対応お願いします」→ 火に油を注ぐ - OK対応:
「以前からのお気持ちをお聞かせくださりありがとうございます。整理して担当より対応いたします」
「過去の蓄積」は否定せず、“整理して対応”という言葉で鎮静化を促す。
第8章:よくあるカスハラ事例【31〜35】と模範対応
事例31:外国人スタッフへの理不尽な差別発言
状況:「外国人が接客するな」「日本語がわからない奴に任せるな」と人種・言語を理由に攻撃。
- NG対応:
「日本語できます!」と感情的に反論 - OK対応:
「対応に不備がありましたら申し訳ございません。責任者よりご説明いたします」
差別的言動は即引き継ぎ。個人を守る姿勢と、毅然とした対応が大切。
事例32:トイレ使用など私的要求を押し付ける
状況:「トイレ貸せ」「子ども寝かせる場所ないの?」など、店舗の設備を超えた要望を執拗に求める。
- NG対応:
「ルールなので無理です!」→ 突き放した印象に - OK対応:
「申し訳ありません。店の規定によりご対応が難しい内容です」
ルールに則りつつ、丁寧な“お断りスキル”を磨くことが鍵。
事例33:長文クレームメールを連日送ってくる
状況:1日に何通も、数千字の長文メールで延々と店舗への不満や攻撃文を送り続ける。
- NG対応:
返信を急ぎすぎて内容に触れてしまう - OK対応:
「ご意見を承りました。本件は責任者にて確認し、必要に応じてご連絡させていただきます」
感情に引っ張られず、“受領→社内確認→選別返信”のルールを徹底。
事例34:子連れを理由に免責や便宜を求める
状況:「子どもがいるんだから優遇しろ」「ミスしたのは子どもが騒いだからだろ」と責任転嫁。
- NG対応:
「それは関係ありません!」と否定 - OK対応:
「状況は理解いたしました。内容を整理して責任者がご案内いたします」
相手の状況に共感しつつ、“公平な判断”と“事実の整理”がカギ。
事例35:警察を呼ぶと脅す・実際に呼ぶ
状況:「警察呼ぶぞ」「もう通報したからな」と言って脅したり、実際に警察を呼ばれるケース。
- NG対応:
「勝手にしてください」→ 責任放棄に見える - OK対応:
「必要に応じて、当方も事実をお伝えさせていただきます」
警察対応は“冷静かつ正確に”。記録が最強の防衛手段になる。
第9章:スタッフを守る仕組みと職場の安全対策

- クレーム対応フローの「見える化」
- インカムや緊急ボタンの設置
- 勤務中の定期声かけ・フォロー体制
- カスハラ発生時の記録テンプレートの整備
- メンタルヘルスサポートの外部連携
対処よりも“予防と仕組み”が重要。現場任せではなく「体制」で守る店をつくる。
第10章:トラブル後のフォローとチーム内共有の実践
- トラブル対応報告書の簡略化
- チーム朝礼・終礼での情報共有
- トラウマケア・聞き取り面談
- 本部への報告・改善提案サイクル
「終わったあとが本番」。スタッフを一人にしない、振り返りの仕組みが信頼を生む。
最終まとめ:スタッフの安全と尊厳を守る店舗づくりへ

カスハラ対応は、個人のスキルだけでなく「組織」としての備えが何より重要です。
- NG対応は、火に油を注ぎスタッフを追い詰める
- OK対応は、冷静な距離感とチームで守る姿勢
- 事例と対処法を全スタッフで共有することが抑止力になる
- 職場が“スタッフを守る”空気になってこそ、お客様への質の高いサービスが実現する
現場で戦うスタッフの尊厳を守ることが、お店の信頼と未来を守ることにつながります。
参考資料・出典
本記事は、以下の公的機関・信頼性の高い資料を参考に再構成しています。
- 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(PDF)」
企業向けに作成された公式ガイドライン。対応手順や予防策を網羅。 - 東京都産業労働局「カスタマーハラスメント対応ハンドブック」
中小企業向けに発行された実践的な対処フローや接客用文例を掲載。 - 労働政策研究・研修機構(JILPT)「カスタマーハラスメントに関する調査報告書(PDF)」
現場実態や被害傾向を調査した報告資料。対応マニュアル策定の背景資料として有効。
これらの資料を基に、現場で活用しやすいよう再構成・編集した内容です。
法的判断や企業方針への適用時は、顧問や上司と連携の上ご活用ください。
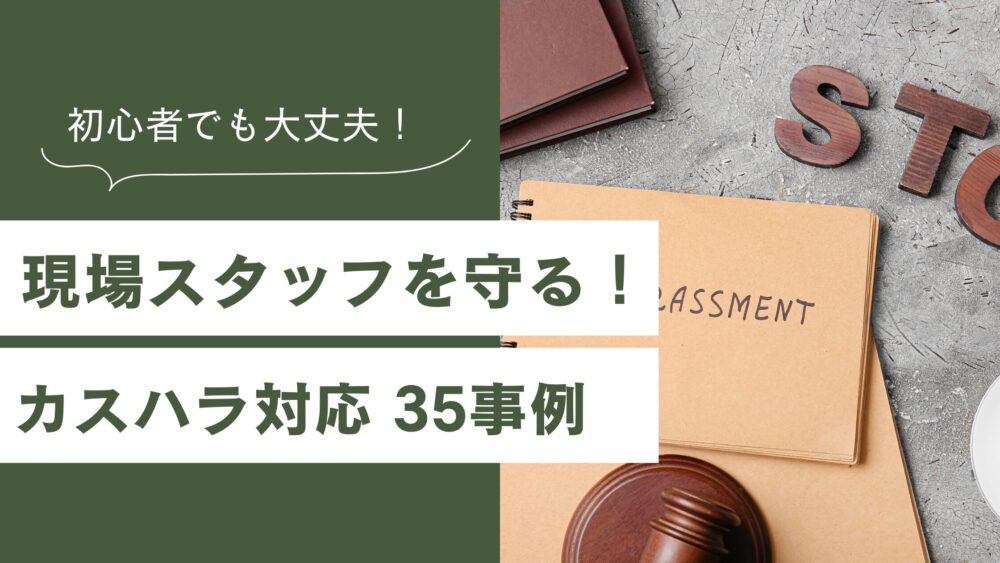


コメント