スーパー運営の基本
はじめに
「どの商品が売れているのか?」「利益に貢献しているのはどれか?」
スーパーマーケットの店長・管理職であれば、一度は考えたことのある疑問です。
しかし、感覚だけで売場を作っていないでしょうか?それではロスや機会損失が発生し、利益を取りこぼしてしまいます。
そこで活用したいのが「ABC分析」です。
これは、商品の販売実績や利益率に基づいて、商品をA・B・Cの3つのランクに分類し、重点的に管理するための手法です。
この記事では、スーパーマーケット初心者でも実践できるABC分析の基礎から、売場づくりや在庫管理への活かし方まで、実例を交えてわかりやすく解説していきます。
ABC分析とは?
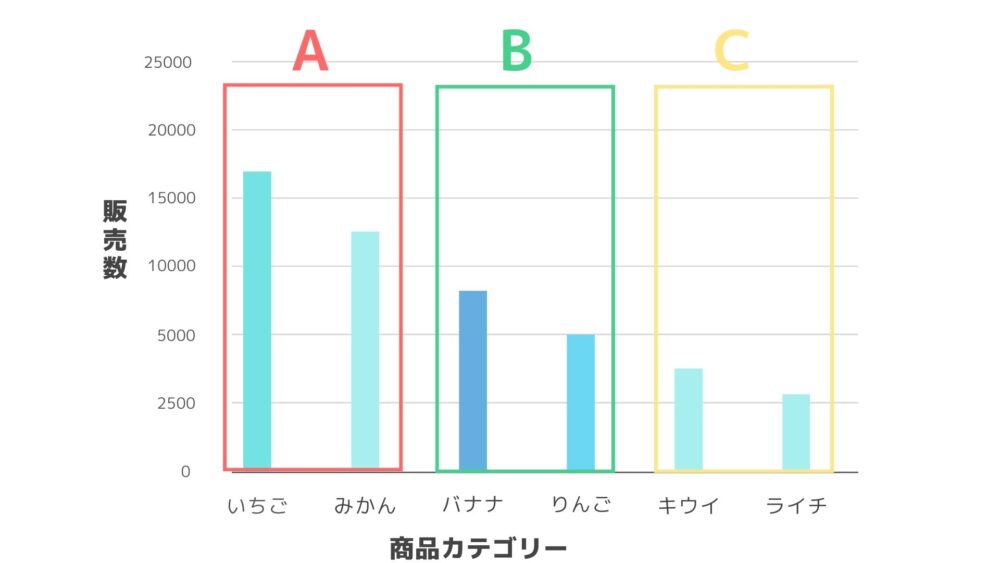
ABC分析の定義
ABC分析は、パレートの法則(80:20の法則)をもとにした管理手法です。
「上位20%の商品が売上の80%を占める」という原理に基づき、商品を以下のように分類します。
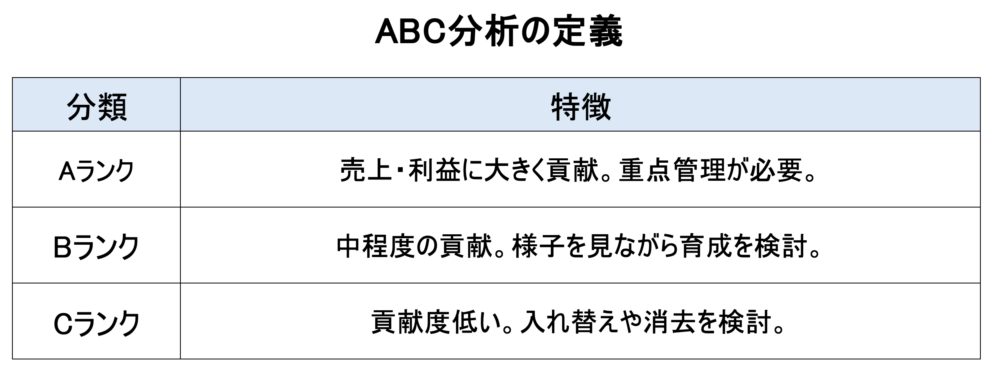
なぜABC分析が重要なのか?
スーパーマーケットでは、商品数が数千〜数万点に上ります。そのすべてを均等に扱うことは現実的ではありません。
ABC分析を活用することで、限られた時間や人材、スペースを「売上・利益に直結する商品」に集中させることができるのです。
ABC分析のやり方(基本手順)
では、実際にABC分析を行うためのステップを見ていきましょう。
ステップ①:分析対象のデータを用意する
必要なデータは以下の通りです。
• 商品コード
• 商品名
• 販売点数 or 売上高
• 粗利額(利益率)
これらのデータはPOSレジやExcelの販売実績から抽出できます。
ステップ②:売上または利益額で降順に並べる
次に、販売点数・売上・利益額のいずれかで降順に並べます。
例えば粗利額で並べた場合、「利益を稼いでいる商品」から順に並ぶことになります。
ステップ③:累計比率を出してランク付けする
累計比率を計算し、以下のようにランク分けをします。
• 上位70%まで → Aランク
• 次の20% → Bランク
• 残り10% → Cランク
この比率は一例であり、店舗の方針や業態により調整可能です。
ステップ④:視覚化する(グラフ化)
ExcelやBIツールなどでグラフ化すると、視覚的に優先順位が分かります。
以下のような棒グラフが典型的です。
(※ここにABC分析の参考画像を貼ると効果的です)
売場作りに活かすABC分析の実例
ここでは、実際のスーパーマーケットでの成功事例をもとに、ABC分析の活用方法を紹介します。
事例①:Aランク商品を強化して売上UP
ある店舗では、ABC分析で発見されたAランク商品に絞って以下の施策を行いました。
• 売場の目立つ位置に展開
• 陳列量を2倍に
• 試食販売やレシピ提案で訴求
結果、売上が前月比で15%アップ。
重点管理の効果が数値で表れた好例です。
事例②:Cランク商品を整理して利益改善
逆にCランク商品は売場のスペースを取るだけで回転が悪く、在庫ロスにもつながっていました。
この店舗ではCランク商品の棚割を縮小し、以下のような対応をしました。
• 類似商品との統合
• 新商品の導入
• 売場スペースの再配置
結果、売場の回転率と利益率が改善され、棚あたりの売上効率も向上しました。
ABC分析と利益率の関係
ABC分析は販売点数や売上金額だけでなく、「利益率」を意識して行うことも非常に重要です。
粗利額ベースのABC分析
売上ベースのABC分析では、単価が高い商品ばかりがAランクに偏ることもあります。
しかし、利益率の高い商品が必ずしも売上上位とは限りません。
たとえば、以下のようなケースがあります。

このように、利益ベースで見た場合に真の“稼ぎ頭”が見えるのが、ABC分析の強みです。
ABC分析の注意点と限界
一時的な売れ行きに注意
季節商品やセール品など、一時的に売れた商品がAランクに入ることがあります。
トレンドや時期要因を加味したうえで評価しましょう。
利益貢献度と売場戦略のバランス
高利益でも回転率が悪ければ在庫リスクが高まります。
また、低利益でも集客力のある目玉商品(集客商品)は必要です。
ABC分析は「万能」ではなく、他の指標(値入率、回転率、客数など)と組み合わせて総合的に判断しましょう。
まとめ:ABC分析は“戦略的”に使うのが鍵
スーパーマーケットでのABC分析は、売れ筋商品・死に筋商品の可視化だけでなく、
• 売場の棚割の見直し
• 販促戦略の立案
• 在庫管理の最適化
• 利益率の改善
など、多くのメリットがあります。
特にこれから店舗を改善しようとしている店長やバイヤーにとっては、「第一歩として導入すべき分析手法」といえるでしょう。



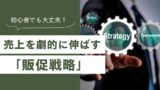


コメント