青果売場はお店の第一印象を決める場所。鮮度管理・品揃え・表示の工夫で、お客様の信頼と売上をつかみましょう。
鮮度管理|“野菜は生きている”を意識する
青果は時間とともに品質が落ちる「生きた商品」。温度管理と先入れ先出しが基本です。
古い在庫を前に出し、新しいものは後ろに配置して、ロスを最小限に。
毎日決まった時間に鮮度チェックを行い、しおれた葉物や傷んだ果物はすぐに撤去しましょう。
見切り販売は、適切なタイミングが重要です。
日々の販売データや天候を参考に、発注の見直しも忘れずに。
「夕方前に少し割引」「夜に思い切った値引き」とルールを決めておけば、無駄な廃棄減らせます。
品揃え|“選びやすさ”が売れる売場をつくる
売場は「たくさんある」より「選びやすい」が大切です。
葉物や根菜など定番商品は種類や量をしっかり確保し、動きの悪い商品は絞りましょう。
お客様が迷わないように、POPで違いを説明したり、陳列をグルーピングする工夫も有効です。
地域や季節に合った品揃えも売場づくりのポイント。
春は山菜、夏は枝豆、秋はさつまいも、冬は鍋野菜など、旬を感じる商品で売場に季節感を出しましょう。
グルーピングとは…関連するものをひとまとめにする、分類する、組み分けることを意味します
産地表示|信頼につながる基本ルール

産地表示
青果は「どこで採れたか」が明確に表示されていないと信頼されません。
法律でも、商品名と一緒に原産地(都道府県や国名など)の表示が義務付けられています。
複数産地が混在する場合は、重量順で全て表示。カットフルーツの詰め合わせなども、品目ごとに明記しましょう。
入荷伝票の内容とPOP・値札が一致しているか、確認をルール化するとミスを防げます。
また、しいたけ等は個別の義務表示があるため注意が必要です。
原木栽培と菌床栽培があり栽培方法を表示するように義務付けられています。
防ばい剤表示|輸入果物は特に注意
輸入オレンジやグレープフルーツなどには、収穫後のカビ防止として「防ばい剤(防カビ剤)」が使われていることがあります。
これらの商品には、使用された薬剤名まで含めた表示が必要です(例:「防カビ剤(イマザリル)使用」など)。
一方で、防ばい剤不使用の国産品や有機商品は、「安心・安全」を訴求できる差別化ポイントにもなります。
参考資料:消費者庁の「早わかり食品表示ガイド」
※最新情報は消費者庁公式ホームページからご確認お願い致します。
陳列方法|売れる並べ方には“コツ”がある

売場の並べ方ひとつで売上は大きく変わります。
• ボリューム陳列:トマトやみかんなどを山積みにすることで鮮度感とお得感を演出
• サンドイッチ陳列:売れ筋商品の間に動きの悪い商品を配置し、視認性をアップ
• ゴールデンライン(目線の高さ):一番売りたい商品はここに配置すると効果的
重いもの(じゃがいも・玉ねぎ)は下段、軽い葉物は上段へ。
カテゴリーごとにエリアを分けると、お客様が探しやすくなります。
売場演出|季節感とワクワクを演出する

青果売場は、季節の移り変わりを伝えられる“舞台”でもあります。
春は山菜、夏は冷やしトマト、秋は焼き芋、冬は鍋野菜など、季節ごとのコーナー展開で「今買うべき商品」が際立ちます。
産直コーナーやPOPで地元農家を紹介するのも効果的。
お客様は“誰が作ったか”を知ると、安心して購入できます。
BGMや照明の工夫、試食(感染対策下では難しい場合も)なども活用し、売場を楽しんでもらえる空間にしましょう。
クレーム対応|信頼を失わずファンをつくるチャンス

どれだけ注意していても、鮮度や品質に関するクレームは避けられません。
対応で最も大切なのは、「誠実な謝罪」と「迅速な対処」です。
• 商品の交換や返金は迷わず実施
• 状況確認と原因の共有を社内で徹底
• お客様への感謝とフォローも忘れずに
クレームは改善のヒント。誠意ある対応は、逆にリピーター獲得のきっかけになります。
まとめ|“見れば分かる売場”を日々つくる
青果売場は、鮮度・品揃え・表示・陳列・演出すべての工夫が結果に直結します。
小さな積み重ねが「このお店は信頼できる」と感じてもらえる売場を作り、売上アップにもつながります。
今日から取り入れられることから一つずつ、見直していきましょう。
お客様に選ばれる青果売場を一緒に育てていきましょう!

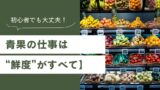





コメント